|
「おい、ニガウリを知っとるだろう」
「はいはい、ゴーヤのことですね」
「うむ、あれは沖縄の名産品だし、形もなんとなく似ているから、『縄』のつくりを使ってはどうじゃろう」
「いいですね。イボイボ感もあるし、尻尾のところがツルっぽいし」
「そう、ツル性だからヤサイニョウじゃな」
「いやあ、またひとつ決まりましたね」 |
 |
「ただひとつ問題がある」 「なんでしょう」 「この字を『ニガウリ』と読むか『ゴーヤ』と読むかじゃ」 「はぁ?」 「ほとんどの野菜は、メインの読み方があるんじゃが、これはどっちかのう」 「どっちでもいいんじゃないですか」 「おい、これは学問だぞ。そんなあいまいなことでどうする」 「でも、普通の漢字にだって音読みと訓読みがあるじゃないですか」 「音読みと訓読み?」 「漢字博士が音読み訓読みに『?』をつけてどうするんですか。そうだ、カタカナっぽい『ゴーヤ』を音読み、ひらがなっぽい『ニガウリ』を訓読みってことでどうですか」 「なるほど、たまにはいいことを言うな」 「うふふ、そうでしょう」 「だがだが、まだまだあまーい!」 「なんですか、いま誉めたばっかりなのに」 「ワシらは新しい漢字を作っとるのだぞ」 「そうですよ」 「だったら、音読み訓読み以外の新しい読み方を考えてもいいじゃないか」 「・・・どういうことですか」 「たとえば、『トウモロコシ』は訓読みで『コーン』はコーン読み」 「駄洒落じゃないですか。しかも英語だし」 「ならば『ナンバ』は大阪読みじゃ」 「確かにトウモロコシのことを『ナンバ』という地方はありますけど、大阪の『ナンバ』は地名じゃないんですか」 「たとえば『ダイコン』は標準読みで『でゃ〜こ』は名古屋読みとか」 「怒られますよ〜」 「たとえば『カブ』は一般読みで『カブどす』は京都読み」 「読みじゃないでしょうが!」 |
 |
「たとえば『スイカ』は当然読みで『スイカズラ』は静岡読み」 「別のモノになっとるじゃないですか!」 「たとえば『ラッカセイ』は普通読みで『パラシュートウ』はアメリカ読み」 「それは『ラッカサン』やがな!」 「いやいや、最後の『トウ』は豆という字を書くのじゃ」 「野菜を一文字で表したいんと違たんかいっ!」 「というわけで『ゴーヤ』はウチナー読みで『ニガウリ』はヤマトゥ読みじゃ」 「じゃあ『レイシ』は?」 「・・・はぁ?」 「レイシですよ。ゴーヤのことをレイシっていうでしょ」 「う〜ん・・・・・あ、お前の背後に髪の長い女性が!」 「それは『霊視』でしょ。『レイシ』ですよ、レ・イ・シ」 「う〜んう〜ん・・・」 「さあさあさあさあ」 「わかった。こうしよう」 「どうするんですか」 「つづく・・・」 「・・・つづかないくせに」
|
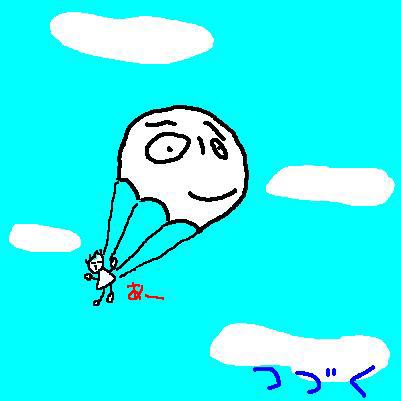 |